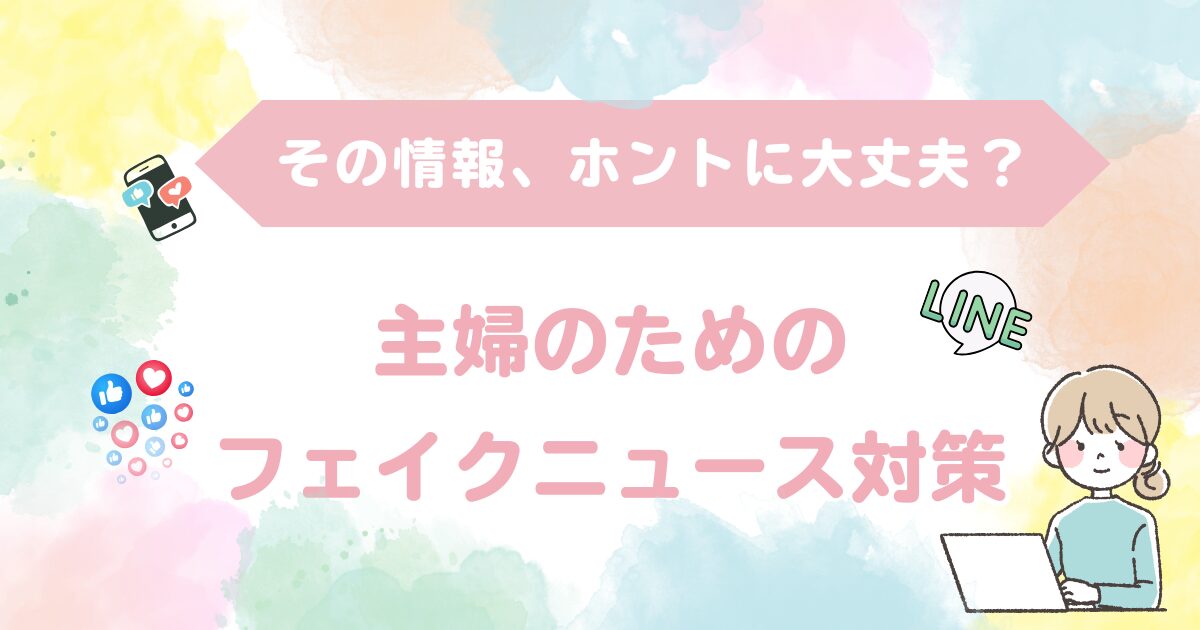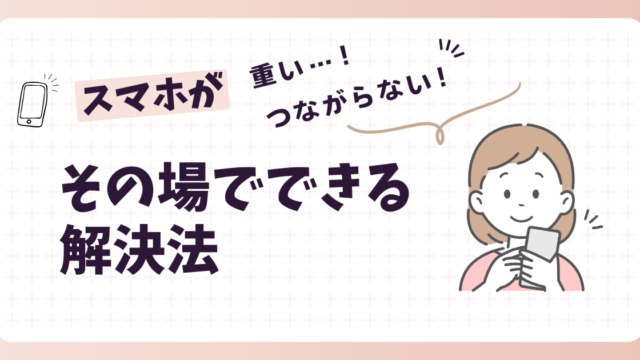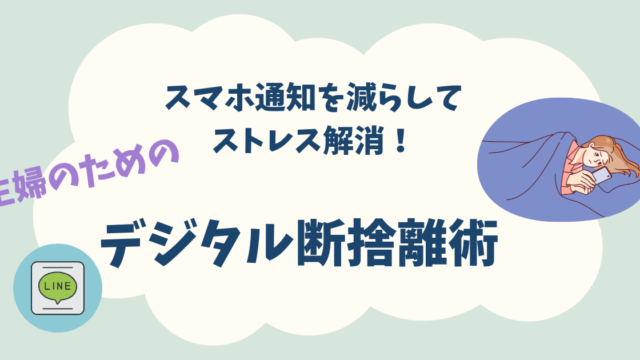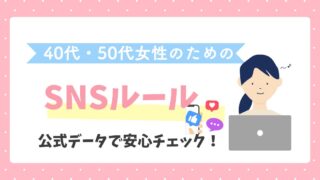ネットやSNSを見ていると
「置いてるだけで除菌ができる!」とか
「飲むだけでやせる!」
なんて、魅力的な商品や広告が目に入ることがありますよね。
私も以前、“置くだけでインフルエンザが予防できる!”と銘打った商品を購入したことがありました…
その商品、まあまあ良いお値段だったので、思い切って購入したのですが…。
後になって消費者庁が「通常の生活環境では効果を裏付ける根拠がない」と措置命令を出した、とテレビで見て、がっかりした苦い思い出があります。
…というわけで本記事では
「情報リテラシー」
「フェイクニュース対策」
というキーワードを押さえながら、主婦の私たちでもやれる“情報に踊らされない安心テク”を一緒に学んでいきましょう。
フェイクニュースの怖さって?
インターネットやSNSが当たり前になった今、私たちは毎日、膨大な量のニュースや広告に触れています。
中には役立つ情報もありますが、実際には根拠のない「フェイクニュース」や誤解を招く広告も混ざっているようです、
しかも、それらは
ちょっと不安をあおる言葉
や
お得に見える数字
など
つい信じたくなるように仕掛けられているから厄介なのです。
主婦世代の私たちは、家族や地域とのやり取りの中で
“情報を受け取る人”
でもあり
“情報を広げる人”
にもなりがち。
だからこそ、誤った情報に振り回されずに、自分だけでなく 家計や家族を守るため正しい情報を見極めなければいけません。
SNSやLINEで広がる「誤情報」の怖さ
「〇〇を飲めば免疫力が上がる!」
「このURLから給付金が申請できます」
SNSやLINEのグループに、そんな情報が流れてきたことはありませんか?
私もSNSで、推しの有名人がすすめる【投資入門講座】が表示されて、思わずクリックしそうになったことがあります。
冷静に考えれば怪しいのに、“推しが推している!”というだけで信じやすくなるんですよね
主婦世代が特に影響を受けやすい理由
40代~50代の主婦世代は“情報のハブ”になりやすいそうです。
家族から「これ本当?」と相談されたり、地域やママ友グループで情報を回したり…。
例えば、フェイクニュースを信じてしまうと、知らず知らずのうちに“誤情報の拡散役”になってしまうことだってあるんです。
私自身もネットの情報を鵜呑みにして子どもに伝えたら「ママ、ネット情報に流されすぎ!」と突っ込まれてハッとした経験があります。
信じてしまえば、誤情報でも、おせっかい魂に火がついて悪気なく拡散してしまうことってありませんか。
真偽不明の情報を伝えるときは、信頼を失ったり、受け取った側に不安を与えてしまわないように情報リテラシーを意識する必要がありそうです。
公的機関も注意喚起を発信中!
この情報、ホントに信じて大丈夫?
と感じたとき、頼りになるのが公的機関の情報です。
総務省や消費者庁、国民生活センターなどは、私たちの暮らしに直結する“誤情報”や“広告トラブル”について、定期的に注意喚起を発信しています。
SNSやテレビのニュースより地味に見えるかもしれませんが、裏付けとなるデータや実際の相談事例がまとめられていて、いわば“信頼のよりどころ”。
私も最近は「迷ったときは公式サイトで確認!」と決めてから、余計な不安に振り回されることが減りました。
総務省が分析!フェイクニュースの傾向とは?
総務省の「情報通信白書」では、フェイクニュースや誤情報は 健康・災害・生活に直結するテーマで広がりやすい と分析されています。
実際、コロナ禍には「特定の食品がコロナに効く」という誤情報が一気に拡散したことがありました。
私も別の食品ですが、「◯◯が免疫力を高めるらしいよ」と友人からLINEが来て、深夜にもかかわらず、急いで24時間スーパーに買いに行こうとして夫に止められた苦い思い出があります。
でも、後々わかったことですが、当然ながらその食品に「コロナに効く!」科学的根拠はなありませんでした…。
こういう経験をすると、「人から聞いた」だけでは安心できないことに気づかされます。
つまり、白書が示すのは「誰もが信じやすいテーマほど、誤情報が拡散しやすい」ということ。
人の不安な心理をついて、誤情報は迫ってくるのです。
消費者庁の実際の相談事例
消費者庁や国民生活センターには、毎日のように「誤解を招く広告」や「定期購入トラブル」の相談が寄せられているそうです。
例えば、いわゆる「初回500円」などの広告に惹かれて健康食品を試してみたら、知らずに「定期購入」契約になっていたパターン。
自動的に毎月数千円の商品が送られ、合計で数万円の支払いになってしまった…というもの。
さらに定期購入をやめたくても、解約の電話がつながらず、結局支払い続けることになった
なんてことも…
こうしたトラブルは全国で起こっていて、2020年にはこの手の相談が5万件以上にのぼったというデータもあります。
信頼できる公式サイトのチェック方法
では、「正しい情報」を得るにはどこを見ればいいのでしょうか。
おすすめは次のような公式サイトです
- 総務省や消費者庁の公式ページ:デマ・誤情報への注意喚起が定期的に出ています。
- 国民生活センター:実際の相談事例が分かりやすくまとめられています。
- 厚生労働省:健康・医療に関する正確な情報が確認できます。
私も最近は「気になる広告やニュースを見たら、まず“公式サイトを1回覗いてみる”」を習慣にしています。
最初はちょっと面倒でしたが、”自分を守るために必要なおまもり”と意識を変えることにしました。
主婦でもできるフェイクニュースの見分け方
フェイクニュース対策というと「専門的な知識がないと難しそう…」と感じる方も多いかもしれません。
でも実は、特別な勉強をしなくても“ちょっとした視点”を持つだけで、誤情報や怪しい広告を見抜ける力はぐんと上がります。
フェイクニュースの見分け方
- タイトルが大げさすぎないか
- 誰が発信しているのか
- 日付や数字に違和感はないか
など、言い方は悪いけど、疑った目で見ると少しずつ感覚をつかむことができるんです。
私も最初は「フェイクニュースを見抜くなんて難しい」と思っていましたが、習慣にすると自然に身についてきました。
タイトルが極端に不安をあおっていないか
「これを食べなきゃ危険!」
「今すぐ申し込まないと損!」
そんな強い言葉に出会ったら、ちょっと立ち止まりましょう。
消費者庁も“誇大表示”や“不安をあおる広告”を問題視して措置命令を出しています。
私も以前「〇〇を飲むだけで痩せる!この広告が終わる前にお申し込みを!!」というカウントダウン式の動画を見て、クリックしそうになった経験があります。
でも、冷静に考えたら「本当にそんな魔法のような商品がある?」って我に返ったんですよね。
日付や数字に矛盾がないかチェック
フェイクニュースや怪しい広告には、「データが古い」 または 「数字が極端」 という特徴があることが少なくありません。
たとえば
「1週間で−10kg!」
「飲むだけでシミが消える!」
などのフレーズ。
冷静に考えると、そんな夢のような結果が簡単に出るはずはないですよね。
消費者庁も、根拠のない極端な表現は「不当表示」にあたる可能性があるとして注意を呼びかけています。
私も以前「この実験で効果が証明されています」という広告を見て、「へぇ〜すごい」と思ったのですが、よく見たら“10年以上前のデータ”。
古い情報には、今になっては、その根拠がないことが明らかになっていることも多いようです。
- 「マウス実験」や「小規模な被験者による試験」を根拠に“人に効く”と宣伝する
- 10年以上前の研究論文を引き合いに出し、最新の科学的知見や否定的な結果は触れない
- 「効果ありとされた一部データのみ抜粋」して、全体像を示さない
複数サイトを見比べる習慣をつける
ひとつの情報だけで判断せず、複数のサイトやメディアを見比べることも大切です。
あまりにもおいしい情報は「複数の情報源を照らし合わせる」ことを第一にしましょう。
私も通販サイトや、食事のお店のレビューを見比べるクセはついていたのに、ニュースや健康情報になるとつい都合のよい情報を鵜呑みにしてしまっていたんですよね。
1.日付は新しい?
- 10年以上前の研究や統計を根拠にしていませんか?
- 情報は最新の状況に合っていますか?
👉 情報にも“賞味期限”があります。古いデータは鵜呑みにしないのが安心。
2.数字が極端すぎない?
- 「1週間で−10kg」「飲むだけでシミが消える」など派手すぎる数字は要注意。
- 「根拠のない極端な効果表示」は不当表示にあたる可能性あり
👉 “魔法のような数字”は、まず疑ってみましょう
3.出典は明記されている?
- 「効果が証明されています」と書かれているのに、出典や論文が書かれていない広告は要注意。
- 公式サイトや論文、厚労省・国民生活センターなど信頼できる機関に裏取りできるか確認。
4. 一部のデータだけ切り取っていない?
- マウス実験や少人数の被験者データを“人に効く”と誇張していないか。
- 否定的な研究結果に触れていない場合も疑ってみる。
5. 複数の情報源を比べた?
- 一つの広告や記事だけで判断しない。
- 公的機関の発表や大手メディアも併せてチェック。
今日からできるフェイクニュース対策
フェイクニュース対策と聞くと「大げさな準備が必要そう」と思うかもしれませんが、実は今日からすぐに始められる小さな習慣で十分に対策ができます。
むしろ大切なのは“完璧に見抜くこと”よりも、“立ち止まって確認するクセ”を持ちましょう。
気になるニュースはまず「Googleニュース」で検索
SNSやLINEで流れてきたニュース
興味をついてくる内容に、「えっ、本当に!?」と信じてしまいそうになることもあると思います。
そんな時は一呼吸おいて、まず 「Googleニュース」で検索すること。
同じ内容が複数の大手メディアで報じられていれば、信ぴょう性はぐっと高まります。
逆に、どこにも載っていなければ「ちょっと怪しいかも…」と判断できますよ。
家族グループLINEでシェアする前に出典確認
「これ役に立つかも!」と善意でシェアした情報が、実はフェイクニュースだったら…考えるだけで冷や汗ですよね。
そんな失敗を避けるコツはシンプル。
“誰が発信しているか”をチェックすることです。
公的機関(総務省・消費者庁・厚生労働省)や大手メディアが出典なら安心度が高まりますよね。
ブックマークに「信頼できる情報源」を入れておく
情報を調べるたびに検索するのは正直めんどう…そんな時は、信頼できる公式サイトをあらかじめ スマホやパソコンにブックマークしておきましょう。
おすすめはこの3つ:
- 総務省「情報通信白書」や注意喚起ページ
- 消費者庁・国民生活センターの公式サイト
- 厚生労働省(健康・医療情報)
私もよく使うのは「国民生活センター」。
広告トラブルや実際の相談事例が載っていて、“あ、これ私が見たやつだ!”と気づくことも多いんです。
お気に入りフォルダに「安心情報」と名前をつけておけば、ワンタップで確認できるようにしておきましょう。
まとめ
フェイクニュースや誇大広告は、興味、関心を引くタイトルで、身近に入り込んできます。
しかし
「ニュースを検索で裏どりする」
「シェア前に出典を確認する」
「信頼できるサイトをブックマークして確認する」
この3つの小さな習慣で、私たちはフェイクニュースに引っかかりにくくなるはずです。
情報リテラシーは難しい特別な知識ではなく、今日からできる生活の工夫。
自分の身を守るためにも、正しく身に着けていきましょう。