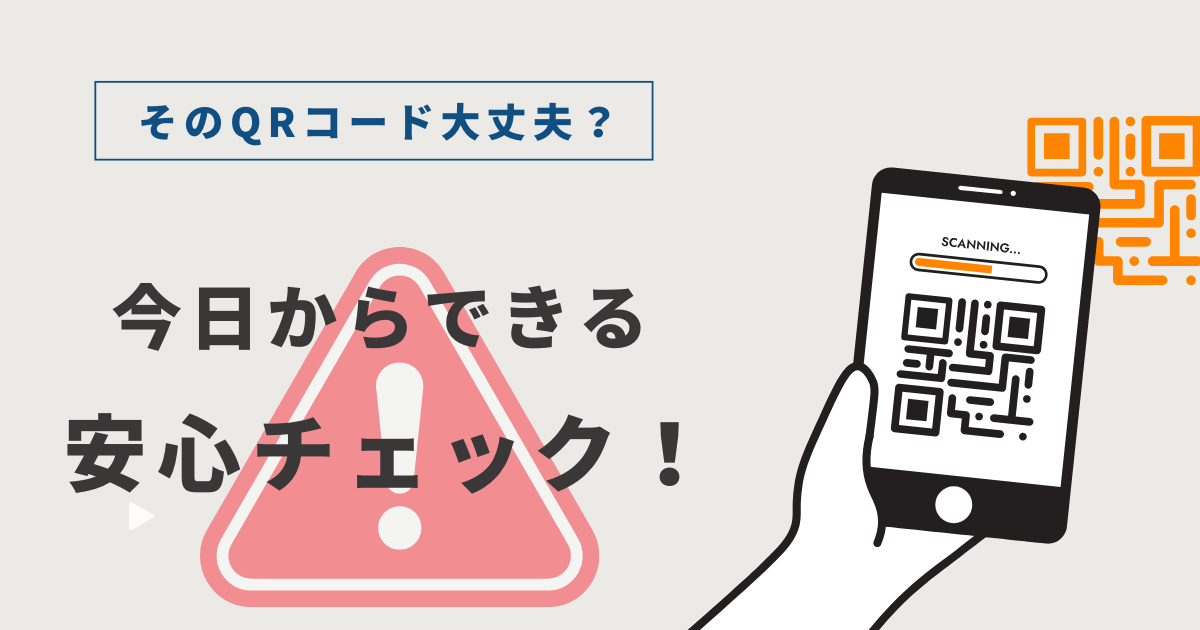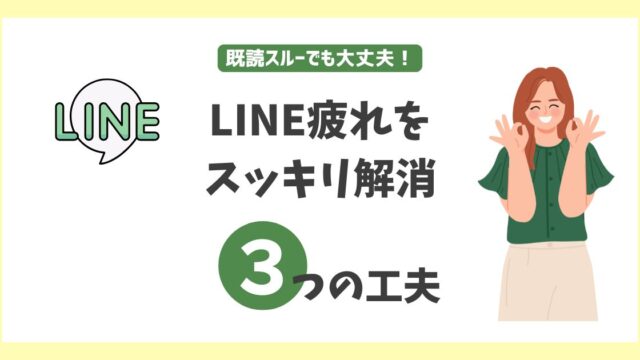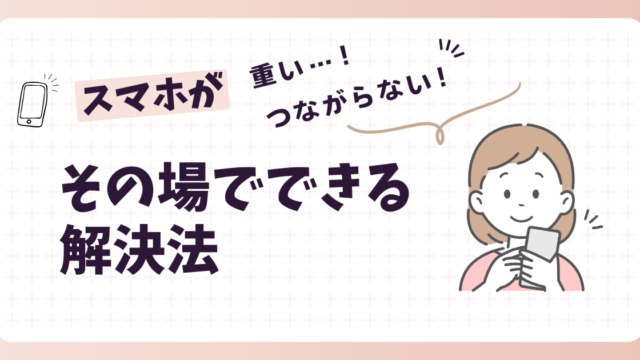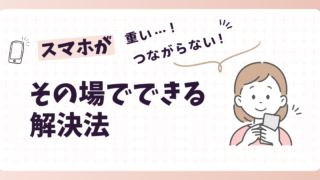こんにちは。もかこです。
今回は、今や便利ツールのひとつになったQRコードに潜む落とし穴についてお伝えします。
今やスーパーのチラシや宅配業者の通知SMS、気がつけば私たちの生活はQRコードだらけ。
「便利だし、つい読み取っちゃう。」
そんな私たちの心理をついた犯罪が実際に起こっています。
以前、ママ友から割引クーポンだと思ってQRコードを読み込んだら、怪しいサイトに飛ばされてしまった、という話を聞いたことがあります。
「まさか⁉」と思ったのですが、調べてみると国民生活センターや総務省でも「偽QRコードによる詐欺」に注意を呼びかけているんです。
なぜ今こんなに問題視されているのか?
それはスマホ決済やキャッシュレスが普及し、ちょっとした油断が「お金」や「個人情報」の流出につながるから。
この記事では公的データをもとに、主婦目線でできるQRコードの安全対策を紹介します。
ちょっと待って!読み取る前に知っておきたいQRコードの落とし穴
買い物や宅配の受け取り、キャンペーン応募まで…。
今やQRコードは生活のあちこちに登場します。
何の抵抗もなく気軽に読み取ってしまいますが、そこに“落とし穴”があるのをご存じでしょうか?
最近はQRコードを悪用した詐欺や偽サイトへの誘導が増えていて、「ちょっと読み取っただけ」で被害に遭う人もいるんです。
増加するQRコード詐欺の手口
QRコードは、よく見かけるし、利用することも多いので油断しがち。
でも、そこにこそ落とし穴があるんです。
最近の相談事例では、店頭ポスターや街頭のチラシに貼られたQRコードが本物と差し替えられていたケースが報告されています。
うっかり読み取ると、正規のキャンペーンページではなく偽サイトに誘導され、個人情報やカード番号を入力させられてしまう…。
国民生活センターには、2024年4月時点で『QRコード詐欺』への相談が累計400件以上も寄せられているそう。
「何も考えずにQRコードを読み取ることは危険!」
そんな時代になってきました。
スマホ決済の普及とともに広がるリスク
ここ数年で一気に広がったのが、QRコードを使ったスマホ決済です。
お財布から小銭を探すより「ピッ」と読み取るほうが早いし、スーパーやカフェでも当たり前に使えるようになりましたよね。
実際、経済産業省の調査によると2023年のキャッシュレス決済比率は39.3%。
さらに2024年には42.8%と目標の40%を前倒しで突破したそうです。
つまり、日本の買い物のほぼ半分がキャッシュレスになりつつあるということ。
便利になった反面、「お金がQRコード経由で動く」時代になったとも言えます。
ここで怖いのは、もし偽のQRコードにアクセスしてしまった場合。
以前なら「変なサイトに飛んで終わり」程度だったのが、今はそのまま決済や個人情報の入力につながる危険性があるんです。
安心してQRコードを読み取るための注意点
”おすすめされるがままについ読み取っちゃう”
そんなQRコードですが、身近なところに落とし穴が潜んでいます。
ここでは、私たち主婦が普段の生活で気を付けたいポイントをまとめてみました。
ちょっとした習慣で、QRコードに対する安心感はぐっと高まりますよ。
見慣れないQRコードは用心する
スーパーのキャンペーンチラシや街頭のポスターにあるQRコード、気軽に読み取ってしまいがちですよね。
でも実際には「本物の上に偽物を貼る」というシンプルな手口も存在します。
読み取る前に、そのQRコード、本物の上に貼られたものじゃありませんか?
“ちょっとでも怪しいと感じたら立ち止まる”──これが一番の防御策なんです。
実際に起きている被害の声
宅配業者を名乗るSMSに載ったQRコードから偽サイトへ誘導され、個人情報を入力してしまった…そんな記事を目にします。
記事を読んでいると「まさか自分が」と思っていた人ばかり。
私自身も再配達の通知SMSを一瞬信じかけて、家族にほんの数秒の油断が“被害者と紙一重”なんですよね。
お金がからむ操作は特に慎重に
QRコードや怪しいリンクは、ただ変なサイトに飛ばされるだけでなく、スマホ決済や口座情報の入力に直結するケースも増えています。
「返金します」と言われても、必ず公式アプリや正規のページから手続きするのが鉄則。
家計を預かる私たちにとっては、「お金に関わるときは必ず一呼吸おく」が安心のルールです。
そのQRコード大丈夫?読み取る前に必ず確認したいチェックポイント
QRコードって、つい“ピッ”と読み取っちゃうけど、その前にちょっと確認するだけでリスクはぐっと減らせるんです。
ここでは、主婦の私でもすぐできる“安心ポイント”をまとめました。
掲示物や印刷物に“違和感”がないか
まずは見た目のチェックから。
お店のポスターやチラシに貼られているQRコードが、妙にテカテカしている・上からシールを貼ったように浮いている
これ、偽物の可能性大です。
スーパーなどで、妙に浮いたQRコードを見かけたら、要注意!
読み取る前にじっくり確認しましょう。
「ちょっと怪しいな」と感じたら、その直感を信じるのが一番のセキュリティ対策かもしれません。
QRコード読み取り先のURLが正規サイトかチェックしよう
QRコードを読み取ったら、必ず出てきたURLをチェックしましょう。
①「https」で始まっているか?
②公式のドメイン(例:.jp、公式ブランド名が含まれる)か?
ここを確認するだけで、かなりのフィッシング詐欺を防げます。
例えば
日本語で表示されているのに、アドレスが「.co.jp」や「.jp」じゃなくて「.com」だったら、ちょっと怪しいかも。
住所が「東京〇〇区」じゃなくて、急に「海外のどこか」になっているような違和感、そんなイメージです。
「あれ?“.com”だけど日本語サイトなのに日本法人のドメインじゃない…?」と不審に思ったことがありました。
面倒に感じるかもしれませんが、URLは“住所”みたいなもの。
怪しい住所のサイトに大切なカード情報を入力する、と考えたら、ブレーキも効くはずです。
アプリ決済は必ず公式アプリから開く
「返金します」
「このQRコードからPayで手続きしてください」
こう言われるとつい信じたくなりますが、ここが最大の落とし穴。
アプリ決済は必ず自分で公式アプリを開いて操作するのが鉄則です。
手法は「このリンクからログインしてください」と書かれたメッセージが届くイメージ。
書かれた通りにタップすると、お金を受け取るどころか、送金させられてしまいます。
アプリ決済は必ずアプリを利用する。
これが鉄則です。
主婦必見!QRコード詐欺に気を付けたい3つの身近なシーン
QRコード詐欺と聞くと、「まさか身近であるはずない!」と思いがちですが、実際は日本でも起きている事案なんです。
しかもターゲットになるのは、スーパーや宅配だけじゃなく、チラシ・フードコート・駐車場といった「主婦が普段よく使う生活シーン」。
私もニュースを見て正直びっくりしました。
「まさかこんな所で?」というケースばかりだからこそ、知っておくことが最大の予防策になります。
ここから具体的に3つの事例を見ていきましょう。
フードコートや店舗のQRコードにも要注意
実は日本でも、フードコートや店舗に掲示されたQRコードが偽物にすり替えられる可能性があると報道されています。
レジ横に置かれた支払い用QRや、テーブルに印刷された注文用QRの上から、偽のコードが貼られるケースが懸念されているのだとか。
考えてみれば、フードコートって不特定多数の人が出入りできる場所。
しかも「お腹すいた!早く注文したい!」というシーンで、わざわざQRコードを疑う人は少ないですよね。
詐欺師にとっては“油断が生まれやすい絶好の空間”とも言えるんです。
チラシに潜んでいた罠──愛知で起きたQRコード詐欺事件
「ただのポスティング広告だから大丈夫」と思っていませんか?
実は、日本でもチラシに仕込まれたQRコードでお金をだまし取られる事件が起きています。
2024年1月、愛知県岩倉市の賃貸マンションに配布されたチラシには「家賃関連の手続き」と見せかけたQRコードが印刷されていました。
住人が何気なく読み取ったところ、公式ではないLINEアカウントに誘導され、指示通りに操作した結果、現金10万円余りをだまし取られる被害につながったのです。
一見すると「ただの家賃案内」にしか見えないこのチラシ。
けれど、QRコードは誰でも簡単に作れて印刷できるため、“信じやすい場面”に紛れ込ませる手口が実際に行われているんです。
私も正直、「ポストに入っているチラシはつい安心して見てしまう」タイプ。
スーパーの広告や宅配ピザのクーポンに慣れているからこそ、警戒心が薄れがちなんですよね。
でもこの事件を知って、「QRコードは“身近に置かれやすい罠”」と意識するようになりました。
自転車シェアや駐車場に潜むQRコードの罠
最近の街中では、自転車シェアリングや無人駐車場の決済にQRコードを使う場面がすっかり当たり前になりました。
スマホひとつで支払いができる便利さは魅力的ですが、その“便利さ”に目をつけた詐欺も報告されています。
手口はシンプル。
本物のQRコードの上に、偽のQRコードシールを貼り付けるというものです。
利用者がそれと気づかずに読み取ると、正規の決済画面ではなく詐欺グループのページに飛ばされ、支払ったお金がそのまま犯人の口座に流れてしまうのです。
全国的にもこの手口は問題視されており、警察やセキュリティ専門家も「公共スペースにあるQRコードは特に注意が必要」と呼びかけています。
特に駐車場やシェアリングサービスは人の出入りが多く、不正なシールを貼っても周囲に気づかれにくい環境。
まさに詐欺師にとって格好のターゲットといえるのです。
主婦でもすぐできる!QRコード詐欺対策の第一歩
「QRコードは便利だけど、やっぱりちょっと不安…」
そんな気持ち、私もよくわかります。
でも大丈夫。
特別な知識や高額なセキュリティソフトがなくても、今日からできる簡単な工夫でリスクはぐっと減らせるんです。
ここでは、私が実際に意識している“小さな習慣”を紹介します。
QRコードを読み取る前に「一呼吸」する
詐欺の手口は「急いでいるとき」ほど狙ってきます。
買い物帰りで荷物が多いときや、夕飯の準備でバタバタしているとき、「まあいいか」とQRコードをパッと読み取ってしまう…。
でも、そこで「ちょっと待って、本当に大丈夫?」と一呼吸おくだけで被害を防げることもあるんです。
深呼吸一回が“セキュリティソフト”だと思えば安いものですよね。
公式アプリからアクセスするクセをつける
支払い、再配達、返金──こうした“お金に関わる操作”は、必ず公式アプリや公式サイトから行うと決めてしまいましょう。
私も以前、マンションの管理会社からのお知らせの掲示物に掲載されたQRコード見て疑ったことがありました。
『これって本当に管理会社?』と気になって、公式に電話で確認したことがあります。
結局それは本物でしたが、今の時代、疑心暗鬼くらいになるほうが最強の防御なのではないでしょうか。
スマホのセキュリティ設定を見直す
意外と忘れがちなのがスマホの設定。
カメラアプリの「QRコード自動読み取り」をオフにしておくと、うっかり怪しいコードをスキャンしても即アクセスせずに済みます。
さらに、無料のセキュリティアプリを入れておけば怪しいリンクをブロックしてくれることも。
難しい設定は不要で、「とりあえずオフにする」「とりあえず入れてみる」くらいの気軽さでOKですよ。
不安を感じたら家族に確認する
「これって怪しいかも?」と感じたら、一人で判断せずに家族や友人に聞いてみるのも効果的。
QRコードではないのですが、ショートメールに届いた通販の不在通知が届いたときのこと。
「このSMS、本当に宅配業者かな?」と夫に見せたら「怪しすぎるよ!」と一蹴されて助かったことがあります。
自分だけだと冷静に判断できなくても、誰かに見てもらうと意外とすぐ見抜けるんですよね。
まとめ
QRコードは私たちの暮らしを便利にしてくれる一方で、偽物に誘導されて詐欺や不正請求につながるリスクも隣り合わせです。
フードコートの注文用コードやポストのチラシ、駐車場の決済など、身近な場所に落とし穴は潜んでいます。
でも、読み取る前に一呼吸おく・公式アプリから操作する・不安なときは家族に確認する──この小さな習慣だけで、被害はぐっと減らせます。
安心して暮らすために、今日から“ちょっと待って!”を合言葉にしてみませんか?