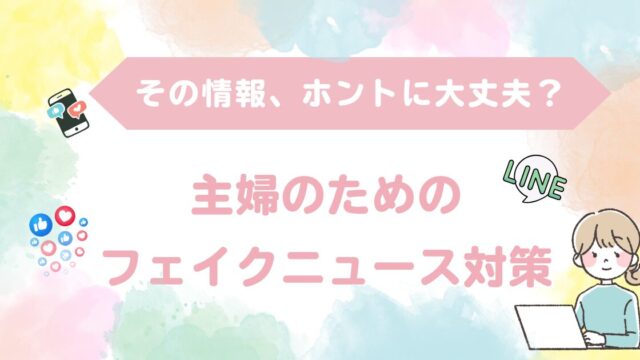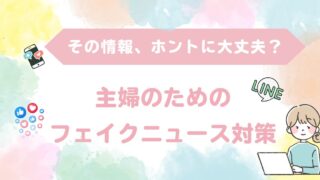こんにちは。もかこです。今日はSNSを原因とした危険の回避について考えてみたいと思います。
「SNSってなんだか怖い…」そう思うのは、あなただけではありません。
”何気なくSNSに投稿した写真から自宅を特定された” とか
”リアルタイムで外出先の様子をアップしたせいで、空き巣の被害にあってしまった”とか
安易にプライベートの様子をSNSで発信したせいで、思わぬトラブルに合うことが増えています。
しかし安心してください!
ほんの少しルールを知るだけで、SNSは危険なものではなく、むしろ暮らしを豊かにする道具になります。
この記事では、公的データや信頼できる情報をもとに、40代・50代女性が安心してSNSを楽しむための入門ルールをやさしく紹介します。
「私だけじゃなかった!」40代・50代女性がSNSに不安を抱くワケ
SNSが若い世代だけでなく、いまや大人世代にもすっかり広がってきました。
家族や友人とのやりとり、趣味の情報収集、買い物やニュースチェックまで、私たちの生活に欠かせないツールになりつつありますよね。
でもその一方で、「便利なのはわかるけど、やっぱりちょっと怖い」という声も少なくありません。
なぜ、利用者が増えているのに不安を持つ人が多いのでしょうか?
それでもSNSに不安を抱く大人世代の本音
SNSの利用者は年々増えていて、もう「若い人だけのもの」ではありません。
調べによると60代の約9割がSNSを利用しており、70代でも7割近くが日常的に使っているそうです。(NTTドコモ モバイル社会研究所による2025年1月時点の全国調査結果に基づいています)
つまり、中高年でも「SNSは苦手だから…」と避けている人は、少数派なんですよね。
それだけ中高年層のSNS利用が広がっているのに、SNSに対する「怖い」という気持ちは消えていないようなのです。
私自身もそうでした。
SNSのアカウントを作りたての頃は、”アンチなメッセージがきたらどうしよう”と不安で、ひとつも投稿せず、半年間ほったらかしにしていたくらいです。
そんなSNSを怖がる背景には、40代・50代ならではの「情報との付き合い方のギャップ」があるようです。
若い世代は学生時代からSNSを当たり前に使いこなしてきましたが、私たち世代は途中から“後追い”で学ぶことになった世代。
だから「みんな使っている」状況に追いつく一方で、どこかで「やっぱり怖い」という違和感が残ってしまうのです。
友人との会話でもよく出てくるのは
「見るだけならいいけど、投稿するのは不安」
「便利そうだけど、何かトラブルがあったら怖い」
といった声。
私も初めてInstagramに写真を投稿したときは、アンチコメントが来ていないか、と心配で、夜中に「やっぱり削除しようかな…」と、何度も投稿を確認していました。
9兆円もの被害も…SNSに潜む危険をデータでチェック
SNSは「ちょっと便利な道具」として広がりましたが、使い方を誤ると大きなトラブルにつながることもあります。
しかもそれは一部の特殊な人だけの話ではなく、私たちの日常生活にも身近に起きていること。
では実際に、「SNSに潜む危険」を公式データをもとに見ていきましょう。
定期購入・詐欺広告でのトラブル
「お試し980円!」──この言葉に心惹かれたこと、ありませんか?
私もつい申し込んでしまい、翌月から8,000円の定期購入コースに切り替わっていたことがあります…。
解約の電話をかけても、なかなかつながらず、ホントに時間をムダ遣いしている感覚でした。
消費者庁の「令和7年版 消費者白書」では、2024年の消費者被害総額は約9兆円に達したと報告されています(推計範囲は8.5〜9.6兆円)。
年間1,940万人が消費者の立場で何らかのトラブルを経験し、その半数以上が金銭被害を受けたそうです。
SNSがきっかけだったケースも含まれており、『便利だけど怖い』という感覚は決して大げさではありません。
誤情報・デマの拡散
「○○を食べれば病気が治る!」
「スーパーで卵が品切れ!」
SNSにはつい信じたくなる情報が次々に流れてきます。
でも、総務省の調査では偽・誤情報に接触した人のうち47.7%が『正しい』と思い込み、その25.5%が拡散していたそう。(総務省:2025年 「ICTリテラシーに関する実態調査」)
私も「閉店半額セール情報」を鵜呑みにしてスーパーへ走ったら、閉店でもなく、通常価格でがっかりした経験があります。
こうして情報に踊らされる背景には「みんながシェアしているから本当らしい」と信じてしまう心理があります。
真偽不明の情報は、「一呼吸おいて確認する」ことが大事だとつくづく思い知らされました。
個人情報の漏えいリスク
SNSに投稿した何気ない写真やコメントから、住所や生活パターンが推測されることがあります。
警察庁も「旅行中のリアルタイム投稿」には注意を呼びかけており、実際に空き巣被害につながった事例も報告されています。
私も温泉旅行の写真をその場でアップしたら、近所の方に「留守がバレてしまいますよ」と言われてゾッとした経験が…。
それから、リアルタイムで外出先での出来事をアップするのを控えています。
安心して使うためのSNS入門ルール
「SNSは怖い」と思う理由の多くは、“知らないうちに危ない目にあってしまうかも”という不安です。
でも、ちょっとした習慣を身につけるだけで安心度はグンとアップします。
ここでは、私自身の失敗から学んだ“やさしい入門ルール”をチェックリスト形式で紹介します。
✅ 広告は“一晩寝かせて”から判断
「限定◯名様!今だけ特別価格」
こういうフレーズを見ると、つい“今買わなきゃ損する”気分になりますよね。
私は以前、夜中にスマホを見ていて勢いでポチっと押しそうになったことがあります。
翌朝冷静になって見返すと「本当に必要かな?」と疑問が湧いて、そのままスルー。
結果的に無駄な出費を防げました。
消費者庁も、SNS広告による定期購入トラブルが急増していると注意喚起しています。
背景には、広告がいつも見慣れているフォロー主の投稿と同じ画面に流れることで“信頼できそう”に見えてしまう心理があります。
👉 SNSに流れてくる商品の購入は「その場で決めない、一晩寝かせる」というルールを徹底しましょう。
投稿写真の位置情報はオフに
「見て見て!旅行先の絶景!」
旅行先での出来事はてテンションが上がって、その場でSNSに投稿したくなりますよね。
ところが写真には位置情報(GPS) が残っていることもあります。
悪意のある人からすると「今この人はココにいるから家は留守」と一瞬でわかってしまうのです。
私は以前、友人が“今、家族と〇〇温泉に来ています”とストーリーに投稿していて、「これ大丈夫かな…」と心配になったことがあります。
本人は「ただの思い出投稿」のつもりでも、他人から見れば立派な“居場所の公開”なんですよね。
👉 投稿は「帰ってからまとめて」がおすすめ。安心感が違います。
✅ 拡散する前に「ほんと?」と声に出して確認
SNSを眺めていると「健康法」「節約ワザ」「災害速報」など、シェアしたくなる情報が流れてきます。
でも総務省の調査によると、誤情報に接触した人の半数近くが“正しい”と思い込み、4人に1人は拡散していたんです。
私もコロナ禍の頃、「トイレットペーパーがなくなる!」という投稿を信じて慌てて買いに出かけた経験があります。
ご存じのとおり、トイレットペーパーが買占めによって無くなっただけで、数日後には店頭にいつもの値段で並んでいました…。
👉 シェアする前にひと言「ほんと?」と声に出すだけで冷静になれます。
✅ 公式アカウントをフォローして正しい情報源を確保
「どの情報を信じればいいのか分からない…」と感じたら、頼れるのは公式アカウントです。
自治体や警察、総務省などが発信する情報は、信頼度が段違い!
私の地域では、去年の大雨のときに市役所の公式LINEで「避難所開設」のお知らせが流れてきました。
ニュースより早く、しかも正確。
あのときは本当に助かりました。
👉 友達の再投稿に頼るより、まずは公式アカウントをフォロー。
安心してSNSを使える“安全網”になります。
主婦こそ得する!40代・50代女性のためのSNS活用術
「怖いから使わない」ではもったいない!
SNSは正しく使えば、むしろ毎日の暮らしをちょっと楽しく、ちょっと便利にしてくれる道具です。
ここでは、私自身が「これいいな」と実感した活用アイデアをご紹介します。
🌿 節約情報をキャッチして家計にプラス
SNSは、実は節約の宝庫。
自治体の公式アカウントをフォローしておけば、「光熱費の補助金」「ごみ袋の無料配布日」など、暮らし直結のお得情報がすぐ届きます。
私はそこで「エアコン買い替え補助金」を知って、なんと2万円も得しました。
テレビや新聞より早かったのが驚きです。
またInstagramの「#業務スーパー節約」「#コストコ戦利品」をのぞくと、リアルな主婦の節約テクが満載。
レシピや保存法など「今日マネできる」アイデアが次々見つかります。
🌿 趣味や学びの仲間が見つかる
大人になってから新しい友達を作るのは難しいもの。
でもSNSなら、共通の趣味を持つ人と気軽につながれます。
私は布小物づくりが好きで、Instagramで「#ハンドメイド好きさんと繋がりたい」を検索したら、同じ布で作品を作っている方からコメントが。
そこから交流が広がって、まるで同じサークル仲間のように楽しんでいます。
最近は「節約・家計見直しチャット」や「オンライン読書会」などSNSでの学び直しコミュニティも増えています。
🌿 遠くの家族や友人との距離をグッと近くする
SNSは、離れて暮らす家族や友人との距離を縮めてくれるツールです。
例えば、子供たちから楽しい学生生活の様子の画像が送られてきたり、遠くに住む学生時代の友達とグループLINEで盛り上がったり…。
電話だと気を使う相手にも、”変な間”を気にすることなく、コミュニケーションをとれるのもSNSならでは、ですよね。
「一人で悩まなくて大丈夫!」SNSトラブル時の相談先ガイド
SNSを安心して使うためには、「もしもの時に頼れる場所」を知っておくことが大切です。
実際にトラブルに巻き込まれると、「誰に相談したらいいの?」「これって警察沙汰なの?」と頭が真っ白になりがち。
そんなとき、公的な相談窓口を知っているかどうかで安心感が全然違います。
☎️ 消費者ホットライン(188)
「通販で解約できない…」「広告と違う商品が届いた!」といった買い物トラブルはここ。
電話番号は 188(いやや!) と覚えやすいです。
全国の消費生活センターにつながり、専門の相談員が状況を聞いてくれます。
私も定期購入トラブルで相談したことがありますが、「同じような事例は多いですよ」と優しく対応してもらい、すごくホッとしました。
☎️ 警察相談ダイヤル(#9110)
「孫を名乗るLINEが届いた」「怪しいメッセージがしつこい」など、不安を感じるときはこちら#9110へ電話を。
緊急ではないけれど不安…というときに便利です。
各都道府県警察の本部につながり、「これは詐欺の可能性があるか」「どう動けばいいか」を教えてくれます。
👉 「110は大げさかな…」と思ったときの“中間窓口”として覚えておくと安心です。
🌐 国民生活センター公式サイト
「同じような被害に遭った人はいるのかな?」と思ったら、ネット検索よりまず国民生活センターの公式サイトへ。
実際の相談事例や最新の注意喚起が掲載されていて、読むだけで「なるほど、こういうケースがあるんだ」と気をつけられます。
記事のネタにもなるくらい、情報が充実しています。
🏢 自治体や省庁の公式SNSアカウント
公式サイトだと、SNSそのものが安心できる情報源にもなります。
災害時や防犯情報は、自治体や総務省・警察庁の公式アカウントで発信されるので、普段からフォローしておくのがおすすめです。
実際に私の地域では、大雨の際に市役所の公式LINEから「避難所開設」の通知が届き、早めに避難できて助かりました。
👉 こうした窓口を知っているだけで、「何かあっても大丈夫」という安心感が持てます。
トラブルを一人で抱え込まず、遠慮せずに公的機関を頼ってくださいね。
まとめ
SNSは「怖いからやめる」ものではなく、正しい知識と小さな習慣で安心して楽しめるツールになります。
データが示すリスクを知り、広告や情報の見極め方、そして困ったときに頼れる窓口を覚えておけば不安はぐっと減ります。
大人世代だからこそできる、落ち着いた使い方でSNSを味方にしていきましょう。
👉 今日からできることは、まず「公式アカウントをひとつフォロー」してみること。
小さな一歩が、安心してSNSを楽しむ未来につながります。